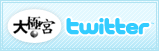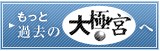大沢在昌・京極夏彦・宮部みゆき公式ホームページ『大極宮』
大極宮公式ホームページ
Since 2001.2.20
特別企画

新刊『おそろし』から、作家生活20年を振り返る
聞き手=東 雅夫 文=吉田大助 「ダ・ヴィンチ」2008年9月号より
百話書きます!
──最新刊の『おそろし 三島屋変調百物語事始』は、まさにタイトルのとおり、おそるべき傑作ですね。同じく江戸ものの怪談集である『あやし〜怪〜』も素晴らしかったですが、今回はそれよりも格段にパワーアップしているなという印象を受けました。いやはや、本当に宮部みゆき、おそるべし(笑)。
宮部 ありがとうございます、嬉しいです!
──いわゆる「百物語小説」は、それこそ鷗外や鏡花の昔からたくさんあるわけですが、『おそろし』は百物語の定型を踏まえた連作短編でありながら、5話から成る一本の長編としても見事な結構をそなえている。読み進めるにつれて、そうした作者の企みが見えてきて、もう興奮するやら物語にのめりこむやらで大騒ぎでした。第2話の「凶宅」あたりから早くも、こんなに濃密な怖さを湛えた作品に接するのは久々だなあ……と思わず舌なめずりしちゃいましたよ。
宮部 もともとこの作品は『あやし』の続編として、この一冊で完結する短編集にするつもりだったんですよ。一話一話がもっと独立性の高いものにしようと思っていたんですけれど、実際に構想を練り出して三島屋という設定を作った時に、「あれ?もしかしたら仕掛けが大きくなっちゃうのかな?」と。
それで、いざ書き出してみたら、第1話の「曼珠沙華」がまず長くなってしまって、「凶宅」を書き始めたら、これも長かった(笑)。途中で方向転換をして、一冊分を書き上げたところで、「これは一冊で終わりじゃなくて、百物語だから百まで書くね」と担当編集さんに言ったんです。
──百話まで書かれるんですか! 作中にちりばめられた布石の多さに、これはただごとじゃなかろうとは思っていましたが、まさか全百話を見越していらしたとは……。
宮部 楽しく書けたのをいいことについ、ツルッと口を滑らせてしまいました(笑)。生家を出て三島屋に奉公へ来た“おちか”という娘が、主人の伊兵衛のはからいで、人々から怪異を聞くことになる。おちかは百物語を聞くことで、若い時に自分の身に起こった悲しい出来事をだんだん、少しずつ葬っていくんですね。これから先も彼女は「変調百物語」を続けながら、恋愛をし、結婚をし、子供を持ち、だんだん年を取っていきます。このシリーズでは、百物語を積み重ねるだけでなく、おちかの一生も書いていきたいんです。
──それはすごい! 一話一話にこれだけの厚みと深みがあるのに、これが本当に百話も続いたら、それこそ史上最大にして最強の百物語小説になりますよ。
宮部 百話の前に、私が死んじゃったら申し訳ないですけど。後半は「寿命との競争だ!」みたいなことになったりしそう(笑)。
宮部流「実話怪談」宣言!?
宮部 『おそろし』を書くうえで、東さんの『百物語の怪談史』というご本をすごく参考にさせて頂いたんですよ。東さんの本で百物語の歴史を知ることによって触発されたし、それからもうひとつ、『新耳袋』にも大いに触発されました。私はこの作品で、実話怪談をやりたかったんです。
──ああ、なるほど!
宮部 聴き手は決まっていて、毎回ひとり誰かが話をしにやって来る。そして会話をすることによって、相手の物語を引き出していく。ですからこの作品は、肝心の怪異が出てくるシーンが会話の中で説明されるんです。小説的な文章で描写するのではなく、「こんな怪異があった」と登場人物に言わせたり告白させるやり方は私、今までやったことがないんですね。『新耳袋』で木原浩勝さんと中山市朗さんが実際に怪談を取材にいく時、「きっとこういうふうに訊(ルビ:き)いているんじゃないかな?」と想像しながら書いていったんです。
──宮部さんは以前から、『新耳袋』を愛読されてますものね。
宮部 だって、聞き書き小説を書きたいと本気で思ったこともあったんですよ。結局できなかったんですが、『おそろし』の連載を始めてしばらくしてから、「私が『新耳袋』をやるとしたらこの形しかない!」と気が付きました。そこからは開き直って、木原さんにお会いした時に「相手がウソを言ってるってわかることはありますか?」「今、話を膨らましているなってわかることはありますか?」「あっ、似たようなパターンの話、聞いたことあるなと思ったことはありますか?」とお尋ねした時の話も書きました(笑)。
──三島屋の主人である伊兵衛とおちかの間で、そんな会話が交わされていますね。読みながら、「おっ、やってるやってる」とニヤリとしちゃいましたが(笑)。しかも『おそろし』では、聴き手と話し手が一対一の、真剣勝負的な百物語になっているのも面白い。従来の百物語小説においては、それこそ元祖たる江戸初期の『諸国百物語』から岡本綺堂の『青蛙堂鬼談』にいたるまで、百物語は単に物語を入れる枠組みなわけですよ。それは『新耳袋』だってそうなんですが。ところが、この作品では枠の部分にも物語が躍動している。枠となる物語と枠の中の物語が、互いにせめぎあう形でテンションも盛り上がっていき、恐怖と感動も盛り上がっていく。その構造自体が、とても新鮮でした。
宮部 百物語はひとつの文化的な伝統で、趣向でもあるし遊びでもあるんだけれども、おちかという娘の場合は、聴き手である彼女自身が切実に、怪異を聞かなくちゃならない理由を背負っている。そこが少し、今までの百物語とは変わっているという意味で副題に「変調」と付けたんです。
──ここまで見事に百物語を「物語」そのものに昇華させた例はないんじゃないでしょうか。史上空前だし、もしかしたら絶後のシリーズになりそうですね。もうひとつ、『おそろし』を読んで愕然としたのは、英国の怪奇作家デ・ラ・メアの短篇『なぞ』──これは宮部さんもアンソロジーに入れていらっしゃる謎めいた名品ですが──の続編というか真相に、まさかこんなところでお目にかかれるとは!ということでして(笑)。物語の核心部分で、宮部さん的な『なぞ』の解釈、それこそ謎解きが成されていることに仰天させられましたよ。
宮部 ご指摘頂きありがとうございます(笑)。この書き方をするなら、「蔵の中には何がいる?」というのが普通はクライマックスだと思うんですけれどね。蔵の中のモノが出てくる時に、「その正体は何だった?」で終わる、という。でもこの作品では、読んでくれた方が、自由に想像してくれるような結末にしたいと最初から思っていたんです。
──それこそは怪談というものの極意でもあるような。そういえば、「蔵」はもちろん、家が軋むだとかふすまを開ける時の怖さだとか、本書には日本家屋ならではの怖さが、いろんな場面で出てきますね。
宮部 空いている屋敷の畳が上がっているとか、雨戸を開け閉めするだけでも大変だ、とか。そういう場面は時代小説ではないと書けないものなので、意識して書くようにしましたし、楽しんで書きました。蔵はぜひ一度、小説で書いてみたかったんですよ。うち(東京・深川)の近所に、質屋さんが持っている古い蔵があるんです。そこはいかにも怪異が住んでいそうな、空襲があって外壁が焦げた跡が残っているような蔵なんですけれど、そのイメージは『おそろし』の中にも入っています。ただ、私はまだ井戸の怖さって書いてないんですよね。続編では井戸を登場させたいと思っているんです。
毎日が百物語に!!
──本書にはお化け話としての怖さももちろんあるんですけれども、それに拮抗するように、人間の怖さも描かれています。それもいわゆるサイコ系の恐怖ではなくて、人と人が関わることによって、しかも決して悪人ではない人たちが関わり合うことによって、そこにどうしようもない悲劇や陰惨さや残虐さが孕まれてしまう。その点も非常に印象的でした。人と人の……これは業(ルビ:ごう)、なんですかね?
宮部 業なんですかねぇ。幸せになろう、仲良くしようと思ってみんな生きているのに、相容れなくなってしまう……。今回、書いていて一番苦しかったのは、話の中で子供を不幸にしていることなんです。特に松太郎という子は生まれてからずっと陰惨な目にあっていますから、「ごめんね」と思いながら書いていました。ただ、そこは江戸という時代背景も大きくて、あの頃は人間が簡単に死んでいったんですね。子供が生まれてすぐに死んだり、親と子がはぐれたりということがよくあった。江戸は子供が不幸な目にあう時代でもあったんだということは、正直に書こうと思いました。その代わり、今のおちかを囲んでいる生きた人たちは、なるべくみんないい人たちにしよう、と。
──ところで今回はこれまで以上に、怪談文芸の先達である岡本綺堂の文体を意識されているんじゃないかと思ったんですが、そこはいかがでしょうか?
宮部 気にしました。百物語、そして綺堂の『三浦老人昔話』や『半七捕物帳』のような「聞き書き」をやるのであれば、あの文体を取り入れたいなと思いまして。連載中も綺堂の本を何度か読み直しています。
──綺堂の文体って、平明で親しみやすくて折り目正しい。それでいて誰でもマネできるかというと、これが実に難しい。その点『おそろし』は……。
宮部 匂いぐらいは似せられたでしょうか?
──いやいや、綺堂の再来といっても過言ではないように感じられる部分がありました。
宮部 今回、怪異のエピソードを考えることはちっとも苦労しなかったんですよ。ただ、とにかく会話が多い。怪異について回想シーンでがーっと語らせる部分と、そこから先、はぐらかすように会話をずらしていくような演出をする時に、読んで下さっている方が「えっ、ここから先が聞きたいのに!」と思って読むのを止(ルビ:や)めるんじゃなくて、その先に興味を持ってくれるように書くにはどうしたらいいんだろう。そこで参考にしたのはやっぱり綺堂の文体、語りだったんです。「その先どうなったんですか、半七さん!」と、読者の方が興味を投げ掛けてくれるような書き方を意識しました。
──岡本綺堂タイプのクラシックな怪談小説、それから欧米の怪奇小説、そして『新耳袋』的な怪談実話と、宮部さんがお好きで読んでいらしたものが、『おそろし』の中には渾然一体と融合していますね。それに、今まさに世間を騒がしているようないろんな事件と、『おそろし』に登場する事件とがシンクロしているなとも感じました。「キレる」若者の凶行であるとか。今この現実さえも作中に呼び込んでしまう、なんとも不思議で魅力的な「器」をお造りになられましたねえ。
宮部 ああ、安心して本の発売日を迎えられます(笑)。そうするとやっぱり、百話完成させたいですね。他の仕事を休んででも(笑)。でも、他の仕事が役に立つこともあるんですよ。『おそろし』を書いていた時も、新聞と月刊誌二つ、四系統ぐらい仕事をしていたんですね。現代ものやSFといった他の作品を書いている時に思いついたアイデアを、江戸もののほうが向いているという判断で『おそろし』に書いたりもしたんです。この百物語シリーズに関しては特に、例えば書き下ろしで3ヵ月かけて1冊書くというやり方ではないのかな、と。自分も生活していきながら、世の中のいろんな出来事を見ながらいろんなものを読みながら、コンスタントに書いていくのが良いのではないかと思っています。
──今年はこれまで以上に怪談文芸が昂揚するんじゃないかという手応えをひしひしと感じていたところなんですが、宮部さんの『おそろし』は、怪談ブーム招来の決定打になりそうな予感がします。
宮部 実は、今年11月から、読売新聞の朝刊で続編の連載を始めさせて頂くことになったんです。
──おお! 毎日が百物語ですね(笑)。
宮部 またすぐ書き始められることが嬉しいし、次は何やろうかなって今からワクワクしています。なにしろ、1冊の連作長編の中だけじゃ回収しきれない伏線も張っちゃったもので。これとあれをどう繋ごうとか、そんなことばっかり毎日考えているんです。書いていてまったく苦にならない、書けば書くほど大好きになる新シリーズをこのタイミングで始めることができて、私は幸せだなあという思いを噛み締めています。

『おそろし 三島屋変調百物語事始』
宮部みゆき角川文庫 705円
江戸は神田にある三島屋は、袋物を売るだけでなく、「不思議な話」を買う商いを始めた──。主人の姪・おちかが百物語の聴き手となり、客人たちが話す怪異と向かい合う。5本の物語はおちかの心を恐怖によって癒していく。