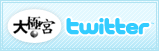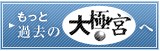大沢在昌・京極夏彦・宮部みゆき公式ホームページ『大極宮』
大極宮公式ホームページ
Since 2001.2.20
特別企画
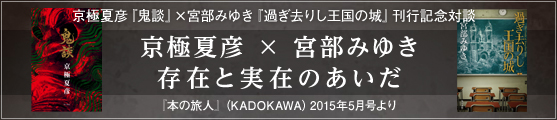
実在しないものの怖さ
京極 宮部さんとはデビュー直後から親しくお付き合いさせていただいていますが、こうしてお互いの作品について詳しく語り合うのって、二十年間で初めてなんですよね。
宮部 そうですね。一度雑誌で対談していただいたことがありますけど、あの時はお化けや妖怪がテーマで、一方的にわたしが色々教えてもらうという感じでした。作品論みたいなものは交換したことがないですね。
京極 仕事柄あちこちでお会いする機会も多いですが、ひたすら関係ない話ばかり。せいぜい「今書いている小説は大変だ」「もう書きたくない」という話題くらいで(笑)。
宮部 (笑)。京極さんの「 」談シリーズは最初の『幽談』の頃からずっと拝読していますが、怖さでいうと、この『鬼談』が一番じゃないでしょうか。すべての短篇が本当に容赦なくって、読み手の胸にぐさっと突き刺さってくる。一方で非常に豊かな物語性を感じたんです。これはどういうことなのかな、というのを今日はまずお聞きしたかったんです。「 」談シリーズは毎回、漢字一文字のテーマがありますね。
京極 テーマというほどではないんですが、今回は「鬼」なのでやや明確な縛りですよね。鬼といっても、多くの方が思い浮かべるであろう、虎皮の褌を絞めて、頭から角を生やしている、あの鬼ではないんですが。鬼という字の本来は、死んだ人、すでに亡くなっている祖先のことでしょうか。つまり存在しないもの、「非実在」ですね。その概念が中国から日本に入ってきて、甚だしいもの、凶暴なものという属性が加わった。この場合、それが善か悪かは関係ないんです。善行も度を超してしまえば、甚だしく、凶暴な感じになるし。容赦ない話になってしまうのは、鬼を描くかぎり必然なんです。
宮部 どの短編もラストの一行がとっても怖いんですよ。「鬼情」にしても、「鬼慕」にしても、それまで張り詰めていた氷に、ぴしっとひびが入る瞬間のような怖さがある。「鬼気」のラストでお母さんが言う「お前の真似だよ」という台詞なんて、自分が言われたらたまらないだろうなと。
京極 ラスト一行についても、図らずもそうなってしまったという感じですね。非実在ですから、物語のどこかで「そんなものはない」と明言しなければならない。一方で、それがなぜ存在しないかという説明をだらだらするのは非常につまらないわけです。結果として「何にもありませんでした」と、読者を突き放すように終わるような構造になりました。
宮部 なるほど。読んでいてどこからこんな怖い文章を思いつくんだろう、と不思議だったんです。不思議といえば「鬼縁」。この作品、わたしには書けません! 江戸時代と現代の物語が交互に描かれて、それぞれで恐ろしい事件が起きるんだけど、二つの事件の関係は最後まで明かされない。でもどうしようもなく繋がって、二重写しに見えてくるんです。
京極 そうですねえ。人はどうしても繋がりを見つけたくなってしまうものなんですね。たとえば、生まれ変わりだろうとか、子孫だろうとか、何か説明しないと気持ち悪い。でもそんな説明しなくても作品は成立するし、そもそも両者に繋がりはないですね。「鬼縁」というのは縁がない、ということですから。
宮部 そうか! 読んでいるわたしが物語を繋げていたんですね。納得しました。個人的な好みでどれか一作選ぶとするなら、「鬼景」が好きなんです。わたしも主人公の女の子と同じように、近所を歩いていて「こんな建物あったっけ?」と首を傾げることが多くて(笑)。そういう経験ってありませんか。
京極 ありますね。建物って取り壊されてしまうと、何が建っていたのか思い出せなくなる。
宮部 主人公だけがありえない建物を見てしまう、という話なんですが、家族の間で交わされる会話がとても長閑で和むんです。「切り株なんかあったら、あたし絶対座ってるし」っていうお姉さんの台詞が可笑しいんですよ。このお姉さん、好きだなあ。わたしも家族とよく他愛もない話をしているので、こういう空気は分かります。近所のパン屋が不味いんだ、というデティールもいいですよね。
京極 近所に昔からあるパン屋って往々にして不味い気がしますが(笑)。美味しいパン屋さんは移転しちゃうのか。読み返してみて感じたんですが、僕はつくづくお年寄りが好きですね。「鬼景」でもやっぱり窓から年寄りが覗いているでしょう。宮部さんを見習ってもっと若者を出さないとと思うんだけど、好きだからつい書いてしまうのね。
宮部 わたしもお年寄りはよく出すんですよ。子供とセットで登場してくるから、あまり目立たないだけで。この作品で窓から覗いているお年寄りは怖いですね。イギリスの怪奇作家M・R・ジェイムスに「小窓から覗く」という作品があるんです。荘園にある木戸の小さな窓から、とても人間のものとは思えない顔が覗いていた、という小品で、わたしはこれが大好きなんです。その印象と呼応しあって、「鬼景」はより一層忘れがたかったですね。そのまま怪談実話の本に載っていてもおかしくないと思いました。
非実在世界との関わり方
京極 『過ぎ去りし王国の城』は、僕も関わっている世界妖怪協会の機関誌「怪」の連載していただいたものです。これまで宮部さんに「怪」で連載していただいた作品といえば『あやし』『お文の影』(『ばんば憑き』改題)で、当然次も江戸怪談だろうと思っていたら、現代ファンタジーで非常に驚きました。今回はどうしてファンタジーを?
宮部 ぎりぎりまで江戸怪談を書くつもりでいたんですが、ふとアイデアを思いついたんです。冬枯れの公園をウォーキングしていたら、作品の中心になるアイデアが浮かんで、「怪」の連載はこれでいこうと。だから物語は冬から始まって、春で終わるんですよ。
京極 といっても、ふと思いつけるようなアイデアじゃないでしょう(笑)。最近の宮部作品にしてはやや短めかもしれないけど、世間的には立派な長編小説のボリュームですよ。
宮部 百五十枚くらいの中篇かな、と思っていたんですけど、書いてみたら一冊分になりましたね。
京極 ウォーキングをしながら思いついたのは、アバターを描きこむことで絵の世界に入りこめる、という部分ですか?
宮部 いえ、作中世界と絵の関わりとか、結末にあたる部分です。主人公が絵の世界に入りこむというのは、割とよくある話ですよね。アバターという概念もテレビゲームをよくするので自然に浮かんできました。ただ、アバターを絵の世界の縮尺にしっかり合わせないといけない、というルールを思いついた時にはちょっと嬉しかったかな。
京極 司馬遼太郎の『果心居士の幻術』はじめ、人間が絵の世界に入りこむというネタは確かにこれまでも書かれています。でも、描かれたアバターの上手い下手が、そのまま異世界に反映されてしまうという発想は小説でもなかったと思いますが。これは発明ですよ。
宮部 やろうと思えば何だってできる舞台なんですよ。絵さえ上手に描いたら、ゾンビの騎士団でも、火を吐くドラゴンでも出すことができる。当初は本当にお城を守っているドラゴンを登場させようと思ったんですが、ハイファンタジー色が強くなりすぎそうなのでやめました。また別の機会に、と思っています。
京極 僕はパクさんというキャラクターが大変に好きなんです。主人公の少年少女を庇護し、導いてくれる役どころですが、とてもインパクトがありますよね。宮部さんが中年男性を準主役くらいの扱いで描くのは、ちょっと珍しい気がします。
宮部 一度こういうキャラクーを描いてみたかったんです。大食いで、優しくて、子供のような心を持った中年男性。パクさんは描いていて自分でも楽しかったです。
京極 いつも黄色い洋服を着ていて、しかもマンガ家の元アシスタントですからね。いいキャラだなあ。
宮部 コミックの世界に詳しくないわたしが、アシスタントさんを描くのは蛮勇かなとも思ったんですが、本職のアシスタントの方に「いいキャラに描いてもらえたら、みんな喜びますよ」と言っていただいたんです。
存在するけど、実在しない
京極 パクさんにしても、主人公の中学生二人にしても、それぞれに問題を抱えている。扱われている事件にしても、かなり重たいものを含んでいますよね。でも、ラストでは各キャラクターにとってちゃんと希望のあるハッピーエンドになっている。いい小説を読んだな、という気にさせてもらいました。人間の醜さや、不可解さを描いた作品が多くなっている昨今、宮部作品のこうしたテイストは貴重だな、と思います。
宮部 この作品については、かなり意図的にハッピーエンドを心がけました。同時期に連載していた『悲嘆の門』という作品は、「存在するけど、実在しない」ものが恐ろしい事件を引き起こす話です。「存在するけど、実在しない」という考えは、京極作品に教えていただいたんですけど、わたしってイヤな人間だな、とあらためて思ったくらい酷い話で。一方がそんな作品だったので、『過ぎ去りし王国の城』では、実在しない世界に働きかけた結果、何かを救うという話にしたかったんですよ。
京極 『門』と『城』は対になっていたんですね。宮部さんの作品はいい意味で安定感があると思います。危なっかしいところがない。これはエンターテインメントの書き手として、非常に大切なこと。だからこそ、どんなに悲惨な展開になっても、読者は最後まで読み続けることができる。同じ書き手としては「ここからどうやって結末に持っていくんだろう」という技術的な興味もあります。『悲嘆の門』だってあんなに恐ろしい話なのに、どこか前向きに終わるでしょう。バッドエンディングにさえ救いがある。
宮部 わあ、それは嬉しいです。今回の作品でも、主人公二人とパクさん、それぞれが一歩を踏み出すところまで描きたかった。
京極 特に若い読者に読んでもらう作品だとなおさらですよね。『過ぎ去りし王国の城』は長さも手頃だし、主人公も中学生の男女ですから、この春新しい門出を迎えた若い人たちにぜひ読んでもらいたいですよね。
宮部 『鬼談』は京極作品初心者にはちょっとだけハードルが高いかもしれませんけど、好きな人間にはたまらない。鬼というテーマを説明するのではなく、言葉そのもので見せてくれる。言葉を使った表現に興味がある人なら、絶対に読むべき作品ですね。「鬼情」でページの下から文章が生えているという文字の組み方なんて、京極さん以外にできないですよ。
京極 あれは苦しい技でしたね(笑)。僕と宮部さんは、作品の印象こそ明暗が分かれますが(笑)、扱うネタはそうかけ離れていないですよね。
宮部 実はそうなんです。魚に喩えると、同じ海流を泳いでいる魚を捕まえて調理している。できあがる料理は違っても、元になる素材は親類同士という感じで。調理法で迷っている時は、京極さんにアドバイスしてもらうのが一番確実。わたしよりはるかに調理道具や技をお持ちですから。近いところでお仕事してきて、京極さんの包丁さばきを間近に見てこられたのはラッキーだったなと思っています。
京極 いえいえ。僕の料理なんてそこらの石ころで、魚を叩きつぶすくらいのものですよ。料理じゃないな、それ。
宮部 だとしても、つみれ料理になるところが凄いんだってば!(笑)
取材・文 朝宮運河