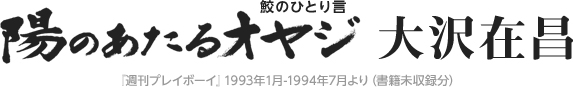世の中はそろそろクリスマスシーズンだが、私は勝浦にきている。このひと月間つづいた締切地獄がやっと一段落し、じきに始まる〝年末進行地獄〟(年末年始と印刷所等が動かなくなるので、そのぶん各雑誌の締切りが前倒しになる)までのつかのまを、短期間の〝ダイエット合宿〟にあてたのである(本音は、今年最後のクロダイ合宿だったりして)。
この原稿は、こちらに着いた日の晩に書いている。明日からは、黒乳首のN君と鮫番のWが合流する予定だ。彼らの目的は、もちろんダイエットではなく、釣りである。
もっとも私は今日、早速、釣りにいってしまった。
夕方、こちらに買出しをすませて到着すると、晩酌用のオカズである、里芋とイカ、タケノコ、シイタケの煮物をちゃっちゃっと作り(ダイエット合宿中は、私は夕食を摂らない。油と肉を排した肴で焼酎を飲むだけだ)、南蛮漬けの材料となる小アジを釣りにでかけた。
馴染みの釣り具店に顔をだし、親爺さんと話す。今年は猛暑の後遺症か、例年に比べ水温の低下が遅れているという。外房では、ついこのあいだまで海水温が二十度あった。
この状態は、東京湾の湾奥部でも同じで、本来ならシーズンインしている筈の冬の釣りもの、カレイが今年はまだあまり釣れていない。カレイは、水温が下がる十一月下旬ごろから産卵のために浅場に乗っこんでくる筈なのだが、今年はそれが遅れている。
海の季節(?)と陸の季節では、ややズレがあって、陸が初冬になる頃、海では秋、ということ(水温の話だ)もあるのだが、それにしても今年はやはり全体にずれているようだ。
アジも本当ならこの時期は、かなり大きなサイズが堤防から釣れてよいのだが、今年は磯では型のいいアジがばんばん上がっているのに、堤防は日によってムラがあり、今日などは、夏に釣れるジンタ(豆アジ)に毛の生えたようなのが、少し釣れただけである。
南蛮漬けを作るにはやや少なすぎる。明日の夜を期待して、今夜の分は干物にでもするつもりだ。
この原稿は、帰ってきてシャワーを浴び、作っておいた煮物と、大根の皮とユズを刻んでひと塩した即席の漬物を肴に、焼酎を飲みながら書いている。
酒を飲みながら原稿を書く、ということは滅多にない。
特に小説は、飲んでいるとたいてい書けない。
単行本『陽のあたるオヤジ』のあとがきにも書いたことだが、思いつくままでに筆をはしらせられるエッセイと伏線と描写に神経をつかわなければならない小説とでは、書く際の注意力の量がまるでちがうのである。
これまでも、酒を飲んで(もちろんホロ酔いていどだが)原稿を書いたことがないでもないが、あとになって読み返すと、同じ接続詩がやたらとでてきたり、まわりくどいだけで結局何がいいたいのかわからない文を書いていたりして、使い物にならないことが多かった。
果たしてこの原稿はどうなのか。もし読者の目に触れたとすれば、明日読みかえしてみて、それほどひどくないのだろう。
酒を飲んで原稿を書くことは少ないが、アイデアを思いついたり、ふくらませたり、という経験は、ときどきある。
酔った状態で音楽を聞いたり、ぼんやりと考えごとをしていると、ふっとした拍子に思いもかけないアイデアが湧くことがある。もちろんそういうときはメモをとっておく。素面になってからチェックするためだ。
ときどき酔いすぎていて、何が書いてあるのかさっぱりわからないメモもあったりする。
酒を飲んで小説を書く、という作家は、それほど多くはない。聞いた話では、ヘミングウェイがそうだったとか、これは御本人から聞いたが、高村薫さんが飲んで書かれるという。
ただし高村さんは、あの小柄、痩身で、滅多やたらに酒が強い。朝八時まで、バーボン、ジンをロックで飲みつづけ、編集者たちの死屍累々の中、いささかも乱れずにいたという逸話の持主なので、多少の酒では文章がびくともしないのだろう。その濃厚で緻密な文体が、アルコールを摂取した指で打ちだされているとは、にわかには信じがたい話だった。
二十代の頃、私は、どうしても酒を飲んでから書かなければならない羽目になると、シャワーを浴びたりひと眠りしたりして、けんめいに酔いをさましてから書いたものだ。
今は、原稿がある日は、とにかく飲まないようにしている。
〝魔がさして〟書いてみたこの原稿は、果たして陽の目を見るかしらん。