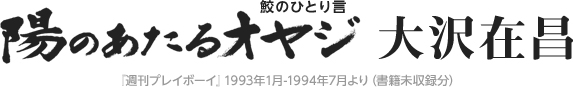この「陽のあたるオヤジ」の七十回分を集めた単行本が発売された。
見本を受けとり、私は久しぶりの興奮を感じた。自分の本の見本というのは、いつでも興奮するものだが、この「陽のあたるオヤジ」の見本は、なんだか初めての単行本をだしたときのことを思いだすような気分に、私をさせた。
小説ではなく、最初のエッセイ集というのがその理由だろう。正直な話、小説ならば、自分の読者の数がどのくらいのものか、おおよその見当がつく。発売されてみて、その数を実際の売れ行きが上回るという嬉しい誤算はあるのせよ、下回ることはめったにない。
それは私が長いあいだ〝本の売れない〟作家だったからだ。自分の本が、「きっと売れる」とは、どうしても思えないのだ。だから、いつも自分の中にあるミニマムの読者数を想定する。
ところが、その読者数というのは、本の形によってちがってくる。本には、四六判ハードカバー、新書判(ノベルス)、文庫と。みっつの形があり、当然値段もその大きさでちがう。
文庫がいちばん安く、四六判がいちばん高い。では文庫が最も売れるかといえば、私の場合、最も売れているのは新書判だ。
本は判形によって読者がちがう、といわれている。たとえば四六判ハードカバーを読む人は。新書判を読まない。また、新書をいつも読む人は、あまりハードカバーに目を向けない、ともいう。
極端なのが文庫の読者で、文庫以外はほどんど本を買わない、という人がかなりの数、いる。
文庫というのはだいたいの場合、オリジナルではなく、すでにハードカバーや新書で売られたものが数年して文庫に入るという形をとっている。
いってみれば、映画とビデオの関係に近い。映画を映画館で観なければ気のすまない人もいれば、ビデオになってから自宅でゆっくり観る、という人もいるのと同じだ。ビデオのレンタル料が映画館の入場料金より安いというのも、ハードカバーと文庫に似ている。
だが、ビデオ派の人であっても、大ヒットして話題になったり、何らかの理由ですぐにも観たい、と思えば映画館に足を運ぶことがある。ビデオになるまで待ちきれない、というわけだ。それは作品のもつ力で、ハードカバーでも、そういう作品はあって、ふだん文庫しか買わない人が手をのばすと、ベストセラーになったりする。
「陽のあたるオヤジ」は、四六判のハードカバーである。定価は千五百円。
高いのか、安いのか。正直いってわからない。私は、自分の小説ならば、「高くはない」ということができる。読者におもしろがってもらうことを念頭に書いてきた以上、たとえば映画館で千五百円を払ってもそれきりなのに比べ、本は一生残るし、嫌なら売れば、そのぶんの数百円は戻ってくる。
しかしエッセイとなるとわからない。
エッセイにももちろんすぐれたもの、おもしろいものはたくさんあって、下手な小説よりよほど感動したり夢中になって読んだ、という経験はある。そういう本なら、千五百円は安い、といい切ることができる。
今のこの気持は、やはり最初の本をだしたときと似ている。自分の書いたものを、それだけの値段の価値があると読者が思ってくれるかどうか、自分では判断できないのだ。
――エッセイなんかいいから、早く小説を書け、あの話のつづきを読ませろ
そう思っている読者もいるかもしれない。それはそれで作家としては幸せなことではある。
「陽のあたるオヤジ」で私は、等身大の大沢在昌を書いた。これは、すべてが作り物の小説とは、やはりちがう。
「陽のあたるオヤジ」がおもしろくないのであれば、それは大沢在昌がおもしろくないのだ。
小説とエッセイは似てはいるがまったく別の作品である。だからエッセイがつまらないといわれても、小説までつまらないといわれたわけではない、というエクスキューズは自分にある。
それでも、つまらないといわれるより、おもしろいといわれたい。本が売れる、というのは、おもしろいの証明の、すべて、ではないが、重要な一材料だ。
だから私は「陽のあたるオヤジ」が売れることを願っている。試され、その結果がでるのを待つ気分だ。
千五百円が高い、と感じる読者は、何年かあとの文庫判でもよい。とりあえず、立ち読みでも読んでもらいたい。
そして大沢在昌への感想を聞かせてほしい、と思う。うーむ、これは宣伝なのだろうか。
たぶん宣伝なのだろう。