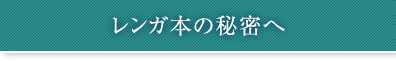

| ―睡眠中の夢って、よく見ますか。 |
| 京極 まあ、夢ぐらい見ますけど(笑)。すぐに眠ってすぐに起きるので、ほとんど覚えてないですね。 |
| ―夢のノートを付けたりするってことはない……。 |
| 京極 僕は、メモやノートって大嫌いなんですよ。広告代理店にいた頃から、打ち合わせなどでもメモをしないんで、こいつは大丈夫だろうかって思われたくらいで(笑)。なぜメモが嫌いかというと、メモって暫定的なものでありながら、最初の「作品」でもあるわけですよね。つまり、完成品に限りなく遠い作品じゃないですか。それが駄目なんです。作品って不完全なものでも、完成してなければならないと思い込んでいる(笑)。途中はないんです。 デザインの仕事でも、普通はスケッチやラフデザインを重ねて仕上げてゆくけど、僕は打ち合わせするやいなや仕上がりと変わりないような見本を作っていた。それが駄目なら、また作り直しましょうという感じの仕事をずっとしてきた。だから小説も制作ノートつけるくらいなら、小説そのものを書いてしまうんです。 |
| ―学校ではどうだったんですか、教室でノートをとったりするのは。 |
| 京極 大嫌いでしたね。黒板に書かれたことや、先生の言ったことを書くわけですよね。それを家に帰ってきれいにまとめて、図を加えたりすると、教科書と同じになっちゃう(笑)。じゃ、教科書があればいいじゃないかって話になる。だからノートとるのって大嫌いでしたね。すごいきちんとしたノートができるか、真っ白か、どちらかでした。 |
| ―きれいなノートができる科目は、何だったんですか。 |
| 京極 社会科のようなグラフや地図とか、ああいう図がたくさんあるものはわりときれいに書きます。だけど、レタリングしたみたいなきれいな字で書かないと気が済まないから、そんなのは続かないんです。授業中にそれをやってると、書くことに集中して、授業内容を聞いてないことになりますから(笑)。 一番嫌いなのは英語でした。アルファベットを書くのがいやだったんですよ。筆記体で外国人みたいにすらすらときれいな形に書ければいいんだけど、そこまで英語を書き込んでいないから形が悪い。線の入ったノートに書いたりするのが、どうしても馬鹿っぽくて、美しくない。 |
| ―そうしたグラフィックなイメージにこだわるようになったのは、なぜなんですか。 |
| 京極 何ででしょうね。日本語って視覚言語でしょ。ひら仮名もカタカナも元は象形文字の漢字で、そういうものには慣れ親しんできたんだから、それは当たり前のことだと思っていたし、文字をただの情報として捉えるのは浅薄な文化だと思っていた節がある。 一方で、音を記号化した聴覚言語としての日本語っていうのもあるじゃないですか。元々それは違うものなんですね。で、結局、人間はどちらかに偏ってくる。 僕はどちらかといえば、視覚的なほうに偏っていったのでしょうか、意識したことはないんですけれども。だから、僕としては実に自然なつもりでいたんですが、最近は少し世の中とずれちゃって、偏執的にこだわる奴と思われているようで(笑)。 |
| ―『絡新婦の理』の場合だと、上の段から下の段にまたがる文章がないですからね。 |
| 京極 あれは全然効果ないと思うんですよ(笑)、小説としてはね。ただ、一方で効果があってほしいという気持ちはある。 例えば一段組四十字詰めというのは、視線がダーッと下がるわけです。その一番下から上に戻るのに長いインターバルがある。二十字詰めなら、間隔はその半分ですよ。全然リズムが違う。そのへんを計算しないでいいのか、という思いがありますね。例えば行末でひとつの単語が分けられると、それは限りなくインターバルを狭めてくださいというしるしなんですよね。 |
| ―急いで戻らなくちゃいけない。 |
| 京極 行末で一旦切れて、上に違う単語がくるときは急がなくていいとか、読み手は無意識に読んでいるはずなんですよ。そうすると新書版ノベルスは、あの版面で読んでくれと信号を発しているんだから、それを気にしないで書くわけにはいかない。最初の『姑獲鳥の夏』は別にして、次からはまず字詰めの通りに書いて、三作目では見開きで収める方向に、四作目では完全に見開きで完結にして、『絡新婦の理』でやっと段組まできた(笑)。 |
| ―文庫化された時のことは……。 |
| 京極 加筆して中身を変えちゃうのは読者として賛成できないですね。 よりよい形にしたいという気持ちは分かるんですが、最初の形で読んだ読者を裏切ることになるとも思いますので……。 作品は野に放った段階で作者と切れるもの、というのが持論なんです。だから僕は、新書判で読んだときとあまり変わらないような印象に直す、というのが正しいと思うんですよ。つまり、漱石の同一作品でも新潮文庫と角川文庫と岩波文庫では、版面が違うので微妙に読後感が違う。どれがいいかは好みの問題だけど、漱石は故人だから聞くわけにもいかない。 で、僕は文庫にするときは手をいれますが、文庫で読んだけど新書で読んだのと印象が変わらないっていうふうに直したいんですよ。そういった視覚的なアプローチがどの程度有効なのかは未知のものですけど、そこにこだわっていきたいとは思います。業です(笑)。 |
| 何層にも重なる物語の どの層を読み進むか、で印象が変わってくる |
| ―あれだけ長いにもかかわらず、読みやすい印象があるのは、そういったところまで可読性を意識しているからなんでしょうね。 |
| 京極 そうならいいんですけどね。読者によっては、今度の『絡新婦の理』はすごく読みやすくて『鉄鼠の檻』の半分くらいで読み終えたという方がたくさんいる。一方で、なんて読みにくいんだという声もあるんです。 つまり、どこを読むかによって違ってくるんじゃないかと思うんですよ。 |
| ―ストーリーを読むか、そうじゃないところを読むか。 |
| 京極 物語にはいくつかの段階がありますから、どの階層に乗って滑るかによって違ってくる。うまく書けてないところに乗った人は読みにくいことになる。言葉の多義性を考慮したうえでも、表面的には一枚の平面ですし、僕の用意したすべての階層がなめらかに起動していればいいんですけど、まだまだですね。 |
| ―執筆は楽しいんですか、苦しいんですか。 |
| 京極 書き終えるまでというのは忍耐ですよ(笑)。書いている間は気分的には楽しいけど、尻が痛いとか指が痛いとか、そういう忍耐ですね。 書いていく過程で出来上がってくる物語なら書き終えたときに達成感があるんでしょうが、僕の場合は書き始めるときに全部決まっているから、執筆時間は短ければ短いほどいい。 僕の場合は構想三十分とか、三日間とか、せいぜいそんなもんですから(笑)。中身が固まるとタイトルもできる。『絡新婦の理』は、最初『絡新婦の鑑(かがみ)』だったんです。『鉄鼠の檻』のカバー予告ではそうなっていた。それを編集長に「鑑と檻は似てるよね」って言われて、あっこれはまずいって思ったわけです(笑)。で、カバーの校正刷りを戻すまでの間に考え直した。この場合、絡新婦というディティールは変えずに、プロットを鑑から理に変えたんですね。 |
| ―どういうことなんですか? |
| 京極 例えばフェミニズムの問題は絡新婦から出てきているんで、これは変わらない。事件自体は少し変わるけど、小道具などは変わらないんです。つまり、鑑だったら理を語る必要がない。ベースに理があったとしても、その上層部分の話で済む。鑑って手本という意味ですから、悪女の手本みたいな、そういう人物を的確に出せば済む話だった。ところが、理にした以上、それを起動させるソフトの話にしなければいけないと、一段階視点を外にずらしたシステム論みたいなものを出さなければいけなくなって、だから予定より少し長くなっちゃった。 今回は同時にいくつもの話が並行して進むんで、どこでスイッチしてもいいんです。視点が四つあって、その四視点が始まりから終わりまで、ずっと通しでいける。スイッチして以降も隠れて進んでいるという形なので、実は書きすぎて隠したり落としたりした部分がたくさんあるんですよ。 |
| ―五作を通じての主要なキャラクターと、何作かに登場するサブキャラクターがいますよね。あの人物たちは、どんなふうに作り出すんですか。 |
| 京極 キャラクターだけ抜き出して造形するっていうことは、ないですね。話の中で必要な人物として造ります。こういう動きをするんなら、こんな来歴でこんな未来があるだろうと、それは話ができた段階で決まっちゃう。一応シリーズだけど、一作品完結で考えてるんです。話の組み立てに必要な部材があって、それにふさわしいのを引っこ抜いてきたり、新しく用意したり、まあ、積み木みたいなもんですね。だからキャラクター小説として読まれても、全然いやじゃないですけど。 |
| ―あの三人組の誰が好きか、とかって言いながら読みますからね。 |
| 京極 最初、自分では意外だったんですが、そういう読み方もありがたいなと思っているんです。ただ僕は、この人物の内面を掘り下げて書きたいというようなことは一切なくて、内面を掘り下げたように書かないと話の構造が見えない場合に書くんですね。そういう意味ではキャラクター重視ではないんです。 『絡新婦の理』の場合は、そういう作中人物に感情移入して読まれる方には少し不満が残る作品かもしれない。あれはシステムの話なので、いっそう個人はどうでもいいところがあるんです。 『魍魎の匣』の木場がよかったという声を多くいただいたのですが、今回も前半では木場が多く出てくる。彼がメインで活躍するのかと思いきや、後半では出てこないから木場の物語としては完結してないし、関口なんか出る幕がない話なんです(笑)。でもどこかでレギュラーメンバー総登場って出版予告が出た(笑)。それはまぁ、結局ラストで出てるんでいいかと。 しかし、読みにくい・読みやすいで意見が分かれるのは、関口が出るか出ないかにもよるようで、関口が出ないとこんなに読みやすいのかという方と、関口が出なかったから読みにくいという方の両方がいらっしゃる。そういう意味で関口はキーパースンなんですね。いちばん現代人的な感覚で、覚めているでしょ。全然傾向の違う読者を結びつける装置になっているような気もしますね。 |
| 狂骨とか絡新婦とか、 いてもいなくてもいい妖怪を大事にしたい |
| ―ビデオを作ったりデザインしたり、漫画を書いたり、いろんな方法があった中で、何故小説家だったんですか。 |
| 京極 ワープロがあったからですよ、職場に(笑)。大会社ならともかく、小さなところだと、自分の仕事が早く終っても他の人がまだ仕事中だと、お先にって帰りづらいときってあるでしょう。だけど、君の仕事手伝おうか、というのは癪にさわる。そういうときには、パソコンやワープロの前に座ってできることをしているのが一番いい。ゲームをやるとピュッなんて音がして分かるけど(笑)、ワープロに向かってれば企画書でも書いてるんじゃないかって思うでしょ。で、書き始めたのが『姑獲鳥の夏』なんですね。 |
| ―どんなふうに小説を発想し、物語が立ち上がってくるんですか。 |
| 京極 例えば『魍魎の匣』なら、箱を囲い込む箱を囲む箱という入れ子構造の物語って、まず考える。それと、そのディティールとして魍魎という妖怪をどうやって沸き立たせるか。魍魎を説明するのでもなく直接見せるのでもなく、魍魎を因数分解して読者の頭の中で再構成されるような言葉を選んでゆく作業があるんです。箱というプロットと魍魎というディティール、その二つが有機的に重なったときに、必要な事件が出現する。その事件を動かすものとしてキャラクターがいるという形なんです。ほとんどいっぺんにできますが。 『絡新婦の理』の場合は、女系の話を書きたいなと思ったんです。女帝とか悪女とかいわれる人たちと、そういった権力を持つ女の手足となる男たちの話ですね。それを、蜘蛛の巣という形で象徴しようと思ったんです。そうすると、その構造に即した展開はおのずと絞られてくる。レベルアップしながら中央に近づいてゆく進行にしよう、といっぺんに考えがまとまったら全部完了という感じでしたね。妖怪の絡新婦をどう消化するか、という民俗学的な考察では少し悩みましたけど。 |
| ―妖怪好きなんですね。 |
| 京極 お化けと真面目に取り組んだ人って少ないから、僕は妖怪に関する自分なりの解釈だけは、できるだけきちんと入れようと思っているんです。狂骨とか絡新婦とか、いてもいなくていい妖怪のことを、たとえ小説という形であっても一所懸命に考える馬鹿な人っていなかったから(笑)。 |
| ―特にどなたかの学説に依拠するということは……。 |
| 京極 『姑獲鳥の夏』を書いたときには、ずいぶん前に読んだ小松和彦さんの『憑霊信仰論』に啓発された部分があって、呪文などは拝借していますから、それは巻末の参考文献に載せました。そうすると、中に書いたことは全部、小松さんの説なんだろうと思われてしまう。実はそうじゃなくて、スタンスもアプローチも結構違ってるんですけどね。同一の見解だとしても、自分なりに消化したものが出ているわけですし……。 だから巻末の参考文献を挙げるときに悩むんですよ、何を参考にしたのかはっきりしない(笑)。でも、絶対にオリジナルということはないんでしょうね。結論は自分のオリジナルだとしても、その考え方の筋道や理論は必ずどこかで読んで知ったことだから、元があるはずだと思うんです。自分で自分の元を探すんだけど、よく分かんなくて……。 |
| ―挙げはじめると全蔵書を挙げなければならなくなる。 |
| 京極 そうなんですね。学術論文もあれば、子供向けのジュブナイルの場合もあるし、それがどちらも僕の中では同列なんです。どんな表現でも、理論だけ抽出すれば同じようなもので、そこで一旦抽象化されたものが作品の中に反映されているんでしょうね。もちろんフィクションですから虚構部分もある。でも、ここまではアカデミックに認められているが、ここから先は認められていないとか、まったくの仮説だとか、それがあからさまに見えたら小説としてバランスが悪いし、読んでも面白くない。だから、参考にしてもらっては困る(笑)。楽しんでいただくのは結構なんですが。 |
| "憑かれたように"ではなく、 テレビを見ながら書いています。 |
| ―文献を見ながらではなくて、完全に咀嚼したうえで一気に書いているスピード感を感じるんですけど、それにしてもどうしてあれだけのものが次々と書けるんですか。 |
| 京極 さて(笑)。よく、憑かれたように書くっていいますけど、あれはあくまで憑かれたようにであって、本当に憑かれて書いたら他人には分からないものになってしまう。一方で一般性に足を着けて、そっちを向いて書かないと作品にはならないですよね。憑かれたように書く場合には「ように」が大事なんですよ。でも僕はそんなことすらなくて、テレビ見ながら書いてますからね。だって、小説を書いて普通に暮らしていたら、テレビを見る時間がないじゃないですか。だから「ドリフ大爆笑」とかを見ながら書いている(笑)。 |
| ―よくそんな器用なことができますね。ラジオを聞きながらという人はいても、テレビを見ながら小説を書くという人はなかなかいない。 |
| 京極 好きなんですよ、テレビ(笑)。いまのテレビはくだらないって意見もあるんでしょうけど、見ている人はたくさんいるわけで、それを知らずにどうして世間のことが分かるのかって思う気持ちもある。僕はビデオの仕事もしてきたから、お金をかけているとか、手を抜いているとか、映像を見れば分かるし、低俗だと思うこともありますけど。それを馬鹿にするのは一般性を軽蔑することにつながっていく気がして、簡単に馬鹿にしてはいけないとも思うんです。 |
| ―逆にいうと、テレビがつまらないから小説を読むという人もいる。 |
| 京極 それがないとは言いませんが、小説を面白く読める人は、つまらないテレビでも面白がれる能力を持っているはずです。所詮テレビってこういう作り方をするんだな、と見ていればそれで十分面白い。 僕はスポーツ番組以外は何でも見ます。スポーツだけは嫌いですね。野球中継の延長で「タモリの超ボキャブラ天国」の時間が繰り下がったりすると、なんだこのお、みたいに憎んでますからね(笑)。 |
| ―作品の映像化の申し込みも、ずいぶんあるんでしょうね。 |
| 京極 かなりきてますけど、難しいんでしょうね。さっきの新書と文庫の話と同じように、映像化するときも、むしろ大幅に変えなければ元の味が出ないということがあるから、そこを変えてやってほしいんですけど、小説のディティールにこだわると失敗する。宝塚歌劇とか吉本新喜劇とか、ものすごいアレンジしちゃえば面白いと思うんですが(笑)。 |
| 専門書も『たのしい幼稚園』も同じに読む 節操のなさが秘訣か? |
| ―ブームといえるほどの人気をご自分で判断すると……。 |
| 京極 僕は基本的にエンターテインメントを書いているつもりなわけで、それはやはり読者を想定しないと成り立たない。一方の純文学が内的な表現の発露だとすれば、それは読者側が能動的な関心を持って近づくことで成り立つことになります。エンターテインメントは、作家の側が読者に近づこうとしているんでしょうね。看板を出しメニューを並べ、きれいなテーブルと食器でごちそうを提供しているわけです。客がそれを食べてまずいとおっしゃるならそれまでです。俺の料理が気に入らないのかって説教するわけにはいかない。味覚なんて人それぞれだし、共通項を見つけるのも難しい。だから、ある程度たくさんの人に喜んでもらおうと思ったら、いろんな部分にさまざまな工夫を施しておかなきゃならない。そういう努力を怠ってはいけない、と思うんです。そのためにさまざまな要素を動員して、サービスに努めなくちゃいけないんでしょうね。 作品の構造がいくつかの階層に分かれていると言いましたけど、それが幾通りもの読み方を可能にする仕掛けとして機能したというのはあるかもしれませんね。 |
| ―面白い漫画を読んだような気分もするし、学術書からインスパイアされたような刺激もあるし……。 |
| 京極 国会中継もドリフターズも同じように見るし、専門書も『たのしい幼稚園』も同じように読んでしまう、僕の節操のなさみたいなものが出ているんですかね(笑)。読者の性別や年代によって面白がっていただける部分が、キャラクターの面白さとか物語の骨格とか、ちょっと先鋭的な小理屈の部分とか、ずいぶん異なっているみたいなんです。何年か経って再読していただいたときに、別な読み方をしてもらえたらうれしいんですけどね。だけど、若い人があんな小説を読んでいると聞くと、少し不気味です(笑)。 |
| ―京極さんが小学生のときに柳田国男を読んでいたような面白さを、京極さんの小説から受け取っているのかもしれない。 |
| 京極 ああそうか、それは考えなかったけど……。僕の本を読んで柳田国男や道元を読んだ人って、いるみたいなんですよ。僕は活字文化の隆盛のためなら何でもやろうって気持ちは強くあって(笑)、だからそれは少しうれしかったですね。僕の本を読むくらいなら、もっとたくさんの本を読んでいるんだろうなあと考えると、うれしかったんですね。 |
おまけ…その1 |
| お坊さんになるノウハウを探していた |
| ―子供の頃は、どんな人になりたいと思っていたんですか。 |
| 京極 小学生の頃は坊さんになりたいと思ってました。僧侶になるには、仏教系の学校に行く手があって、そういう学校を志望してると分かると、寺から勧誘があるんです。住職の子供が跡継ぎにならないと廃寺になるから、坊主になりたい子供がいると養子にして跡継ぎにさせようとする(笑)。そういう養子の話もあったんですが、戸籍をいじってまで坊主になりたくはないと思って断りました。高校も一応仏教系の学校を考えたのですが、その頃はもう知恵がついて、坊さんは寺院経営に忙しくて、求道者たる僧侶を貫徹するのは難しいというのが分かってきて少しシフトしていた。 だから大学では、比較宗教学のようなものをやりたいと考えていたんですが、学校側は美大に行ったほうがいいという。僕は高校では美術部で絵を描いていたんで、芸大に合格すればありがたかったでしょうけれど。それになぜか、すごく反発を覚えた。で、いやになって、じゃ僕は大学に行きませんって宣言して、デザイン研究所に入っちゃった。 |
おまけ…その2 |
| テーマを決めてよく馬鹿な旅行に出かけた |
| ―いま楽しいことって何ですか。 |
| 京極 小説を書いている間も楽しいんですが、それ以外だと子供の世話をしているときかな。子供は三歳の女の子と零歳の男の子のふたりです。生まれる前は子供って好きじゃなかったんですけど、生まれてみると面白いもんですね。 僕は家事や育児は義務としてやるのではいかんと思う。楽しんで積極的にやるもんだと思うんですよ。むしろやらせてくれと(笑)。作家になってよかったのは、そういう時間が取れることですね。 |
| ―旅行などは、どうですか。 |
| 京極 好きなんですよ。若い頃は仲間とよく馬鹿な旅行に出かけましたね。今回の旅のテーマは不良だ! と決めて、不良少年がこの温泉に行ったらどうするかってシミュレーションしたり。新宿から歩いてどこまで行けるか試したり、日蓮宗の寺に行って真言宗の話をたっぷりしてくるとか、日光東照宮の家康の墓の前で鯛の天ぷらを食うとか……。それを撮影しておいて、編集して作った旅のビデオが七十六本ある(笑)。そうやって二次的に旅行を楽しむ面白さも好きでしたね。でも三十歳過ぎると、なかなか仲間も揃わなくなり、それでつまらなくなって小説を書き始めたという面もありますかね。 |
インタビュー・構成・文 野島正幸 |