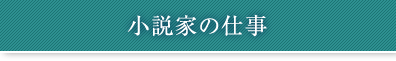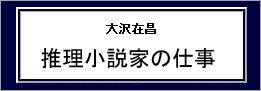| 第1回 執筆日数 |
今月から十二回、私が二十二年間携ってきた仕事の話を書く。同業者や編集者には格段目新しい内容ではないかもしれないが、ミステリの専門誌である本誌読者は、「小説家」という職業に対する好奇心もおもちかもしれない。そこで仕事を題材にしてみることにした。とはいえ、これはあくまで私個人に限った話である。
よく出版界とは無縁の方から、
「一冊の本を書くのにどれくらいかかるのですか」という質問をうける。
答に詰まる。私の場合、本になる作品のほぼすべてが、現在は連載をまとめたものだからだ。したがって一回の掲載量が四百字詰用紙で十五、六枚の週刊誌なら六〜七十週、同じく三枚の新聞なら休刊日を含めると約一年、ということになる。プロはたいていの場合、こうした連載を複数、同時進行で抱えている。
一冊だけで書き下ろしたということになれば、最短は二週間、他はひと月半くらいか。
「小説推理 2002年1月号」収録 |
| 第2回 締切 |
前回の執筆日数にも関連するが、小説家の仕事には当然、締切がある。たとえば本誌の発売日は、毎月二十七日だが、そこから逆算して、流通、製本、印刷、というように販路、工程をさかのぼれば、おのずと、何日の何時までに原稿が完成しなければ間にあわない、という期限が生まれてくる。それが締切だ。むろんのこと、原稿がすぐさま印刷されるわけではなく、校閲、あるいは校正といった、作者・編集者も加わる作業があいだに存在する。校閲とは、原稿に内容的な誤り、たとえば歴史や地理的記述、あるいは作者による勘ちがい(例えば、前号では主人公が事故にあったのは一月とあるのに、今号では二月となっている)などをただすもので、校正とは、誤字や誤植などを直す作業だ。
当然のことだが編集者は余裕をみて締切を設定し(人間だもの、楽をしたいし、何よりいちどきに作業が集中するのを避けたい)、小説家はぎりぎりどこまでひきのばせるか、腹の探りあいをする。とはいえ、十年も二十年も同じ仕事をしていれば、本当の掛け値なしのぎりぎりがいつかはわかってくる。
昔は、本当の締切まぎわに、印刷所まで連れられてきて、書くそばから印刷されるという豪傑作家もいたという。今は、印刷工程の変化などがあって、それはなくなった。とはいえ、ファックスやメールなどの出現で、原稿運搬の作業が簡略化され、実質、締切はのびているのではないか。いずれにせよ、締切なしでは絶対に、原稿とは書かれないものだ。
「小説推理 2002年2月号」収録
|
| 第3回 文章 |
新人賞の選考委員をつとめるようになって、十年近くになるが、表現という意味では、近年の方が、応募原稿の質は高くなっているように思う。
この「表現」と「文章」とでは、私の場合、ややニュアンスが異なる。「文章」という言葉を使う場合、それは小説を構成する複合的な部分をさし、「文章力」とか「文体」といった、書き手の個性にかかわってくる要素である。「表現」という言葉では、書き手のもつイメージを読み手に伝えるための文字の選択をさす。不適格な表現では、作者のイメージが読者に伝わらないし、それで小説が構成されれば、何がいいたいのかわからない作品になってしまう。
この「表現」のレベルが向上しているのだ。これはおそらくパソコンやワープロのソフト機能の向上に負うところも大きいだろう。手書きでの応募原稿はまれだし、私も、どちらで応募すべきかと訊かれれば、ワープロでの応募を勧める。
一方の「文章」だが、これは新人のうちから優れている人は少ない。技術的な側面もあり、「文章は書いているうちにうまくなる」と私は考えている。
想像力の袋が小さい人間が、デビュー後それを倍、三倍に広げるのは難しい。だが文章がさほどうまくない人でも、経験が技術を向上させることは充分にある。
大切なのはやはり想像力だろう。
「小説推理 2002年3月号」収録
|
| 第4回 会話 |
小説の会話と現実の会話は、大きく異なる。あたり前のことだが、会話によって実は書き手の感性のちがいがあらわれる。
現実の会話に近づけようとすると、会話の大半は、意味のない相槌や訊き返しの連続となり、物語を一向に進めることができない。
だが一方で、物語の進展にばかり主眼をおいた会話は、ひどく窮屈なものになる。理路整然として、いかにも説明のための会話、といった印象なのだ。たとえばそれを頭脳明晰な名探偵がくり広げるのならばいいが、物語上「凡人」として扱われているような脇役までもがそうした会話をしていたらどうなるか。読者へ情報は伝わりやすくなるが、どこかおもしろみのない物語ができあがる。
また会話は、登場人物ひとりひとりの個性をあらわす効果もある。全員が同じような口調で喋ると、読者からは読み分けがきかなくなってしまう。性別、年齢、職業、さらには世間との対し方が、短い会話にもあらわれるようにしたいと思っている。とはいえ、若い人間の会話を流行語で埋めつくすと、今度は物語が全体に軽くなり、人物が薄っぺらく見えるという危険もある。
会話の上手下手は、地の文ほどには簡単に差がつかない。だが、人物描写と物語のリズムに、会話は大きくかかわっている。
ミステリの場合はさらに、会話の中に“謎”を解く手がかりを仕込んだりもする。
会話が生きている作品は、登場人物もまた生きている。
「小説推理 2002年4月号」収録
|
| 第5回 主人公 |
推理小説に限らず、小説を書こうとするとき、まず考えなければならないのが、主人公の設定である。
職業、年齢、人生経験、作中に描く描かないは別として、趣味嗜好、信条としていることがら、など。
物語の題材となるのが特殊な世界であるならば、その職業は限定されるし、一般的な“日常”の世界を描くのなら、そうとは限らない。とはいえ、どのような世界であっても“日常”はあるし、ごく“平凡”なできごとでも、特殊な人間の目を通して見れば、まったく異質の世界が広がることもあるのだから、一概に決めるわけにはいかない。
私の場合、多くは、「何を」つまり、どんなストーリーを書くか、ではなく、「誰を」つまりどんな奴を書くか、で小説作りが始まる。物語のスケールに見合ったキャラクターを主人公に与えないと、最後まで背負いきることが難しくなるからだ。
ごくごくふつうの人間がスーパーヒーローのような活躍をすれば、おおかたの読者は鼻白む。また性格的におもしろみのない、目的に一直線といったタイプの人間は、書いていて飽きがくる。
目的に対して進むことはあきらめないが、ときおり道草を食ったり、妙な趣味があったり、ふと人間臭い表情をかいま見せるような奴とつきあっていきたいのだ。
そう、小説を書くとは、主人公とつきあうのと同じなのだ。
「小説推理 2002年5月号」収録
|
| 第6回 塗り絵 |
ミステリ、ことにハードボイルド小説の習作は、ある種の「塗り絵」のようなものではないかと私は考えている。
すぐれたハードボイルド小説は、強い陶酔感をもたらす。洒落た会話、乾いてはいるが詩情のある文体、あるいは心地よい比喩。これらにとりつかれると、自分でも書いてみたくてたまらなくなる。私自身もそうで、十四歳のときから、ハードボイルド小説らしきものを書き始めた。
十代の習作というのは論外であるとしても、このような場合、書き手は必ずといってよいほど、「お手本」とする作家、作品に縛られる。幼児向きの塗り絵本で、輪郭だけが印刷されていて色鉛筆やクレヨンで彩色するものがあるが、それと同じである。
上手に彩色すればするほど、書き手の作品ではなくなっていく。オマージュといえば聞こえはいいが、真似にすぎない。
多くの場合、「もどき」はプロの世界で通用しない。上手な彩色であることは認めてもらえても、それ以上の評価は得られない。
同じ輪郭に色をのせ、なぞりつづけるうちに、やがてはみでる線、手本にはなかった色合いが生まれてくる。そこからがようやく、その書き手の作品となる。
いきなり自分の世界を作りだせる書き手など、そうはいない。結局は、塗り絵を塗り潰す作業を、どれだけ短時間のうちに卒業できるかにかかっているようだ。
「小説推理 2002年6月号」収録
|
| 第7回 ジャンル |
娯楽小説には、いくつかのジャンルがある。推理、時代、風俗、SF、恋愛、などだ。これらは複合することもあるし、さらに細分化される場合もある。たとえば推理小説なら、本格推理、ハードボイルド、冒険、社会派、ホラー、ノアール、などなどで、たいていは帯でうたったり、書評をする上での利便性で決められている。
おおざっぱに分けるなら、推理、時代、そのいずれでもない一般小説、ということになるだろうか。
このうち推理小説は、“強い”ジャンルだと思われているようだ。強いとは、売れるということであり、絶滅しない、という意味でもある。
だが、もちろんのこと、推理小説のすべてが売れるわけではない。推理小説は、ブームがいくつもあった(たとえば社会派、あるいはハードボイルド、新本格など)といわれているが、ブームジャンルの作品がすべて売れたのかといえば、まったくそれはちがう。
ブームを作るのは、そのジャンルに属する、特定の作家に過ぎない。したがって、作家のブームであってジャンルのブームでは決してないのだ。これを誤ると、作家は悲惨なことになる。
ブームといわれるジャンルであろうがなかろうが、しっかりした作品は読者に支持され、そうでない作品は一瞬で消える。
ブームだからとジャンルにこだわれば、その作家の未来は厳しいものになる。
「小説推理 2002年7月号」収録
|
| 第8回 敵役 |
推理小説では、主人公は多くの場合、探偵役である。職業はさまざまだとしても、犯罪の発生そのものを理由に関係者のひとりとなり、客観的な立場を維持しつつも、犯罪の原因、あるいは犯人をつきとめる役割をになう。
したがって推理小説における「敵役」とは、たいてい犯人となる。
犯人役の造形は難しい。探偵役については、これが物語の主人公となることから、作者は早い段階で知恵を絞っている。表向きの職業設定、年齢と経験、風貌、さらには得意な分野と苦手なモノ、などなど。だが、犯人に関しては、その精神性のありようを別にすれば(つまり、異常者であることを証明するためなどの描写を除けば)、詳しく描く機会はそうは与えられない。
たとえばの話、機械のように冷酷非情な殺人者を描くのはむしろ簡単だが、ふつうの人間の心にどす黒い殺意がじょじょに広がっていくのを描くのは、実はたいへんなのである。
若いうちから小説を書き始めた私は、「嫌な奴」を描くのが下手だった。今でも得意ではない。「憎悪」を、紋切り型の表現ではなく描くのは、ある種の才能がいる。ましてやそこに、人間としての魅力を与えるのは、非常に難しい作業なのだ。
だが優れた推理小説には、必ず魅力的な敵役が登場する。敵役がしょぼい推理小説は、主役の探偵も、それに見合った、希薄な存在感しか漂わせていない。敵役の大きさが、物語のスケールを決める、とすらいえる。
「小説推理 2002年8月号」収録
|
| 第9回 客観性 |
すべての小説は、読者に情報を提供することで成立している。そして推理小説の場合は、情報の内容、あるいは、提供の順序を作者が操作することで「謎」を作りだす。
おおかたの推理小説では、情報はすべて文章の中にある。そしてその文章がひとりの作者によって作りだされる以上、純粋に客観的な描写をおこなうのは不可能である。このことが、新人の作品において、大きな障害となるときがある。
つまり、作者に見えているモノがあり、作者はそれについてよく知っているので多言を要するとは思えない。あるいは自分では充分に描写したつもりになっているのだが、読者にはまるで伝わっていない、というケースだ。
小説には当然、文章化されていないが作者の目には見えている世界、というものが存在する。作者はそこからの情報も用いて作品を書いている。書く必要はないが、考えておかなければならない設定などのことだ。ところが読者にはそれに関する知識が皆無であるため、唐突な表現や脈絡のない行動に思えるときがある。
これは熟練した書き手であっても意外におちいりやすい陥穽だ。特に同じ作品を何度も手直ししているうちに起こる。また向かい合っている編集者も、議論を交わすうちに「存在しない」情報をも「読んだ」記憶をもってしまいがちだ。初めて読む読者になったつもりで、作品の情報量を検討する客観性を身につけるのは、実はひどく難しい。
「小説推理 2002年9月号」収録
|
| 第10回 デビュー1 |
この短文を、私は推理小説家を目指す読者に向けて書いている。もちろん推理小説といってもこれまで述べてきたように、さまざまなジャンルがあり、また小説家としてのありようにも、小説家の数だけのスタイルがある。これは、私の知る、あるいは私の考える、「仕事」であって、最大公約数的な「正解」ではない。つまり教科書ではなくて、参考書なのだ。
さて、この数十年、小説家としてプロデビューするには、推理小説が最もその門戸が広いといわれてきた。おそらくそれは事実だろう。
だが、門戸が広ければ、そのぶんデビュー後の生存競争は激しくなる。デビューの近道だとでも思って推理小説を書き、たまたまうまく果たせたとしても、あとがつづかないような人の屍は累々としている。
そのデビューの方法だが、大ざっぱに三つに分けられる。短篇新人賞、長篇新人賞、そしてもちこみである。ちなみに私は、本誌の短篇小説新入賞受賞が、デビューだった。
三つのうち、どれが「有利」か、というのは、多くの小説家志望者にとって切実な問題だろう。もちろん、当人に「実力」があれば関係ない、と断ずる向きもあるだろうが、それはある面正しく、ある面正しくない。なぜなら、基本的にプロデビューするような人間は、あるレベル以上の「実力」をもっているからだ。ではどこで差がつくのか。
それは「運」であり、デビューの方法にも関係してくる。
「小説推理 2002年10月号」収録
|
| 第11回 デビュー2 |
デビュー後の生存率は、「運」とデビューの方法に関係してくる、と前回書いた。それについてつづける。
まず新人の書き手に最も大きな影響を与える「運」とは、担当編集者(以下担当者)との関係である。
ドラマなどで、担当者が書き手につききりになっている場面があるが、あれは「理想的な幻想」というものだ。実際は出版社や編集部の規模にもよるが、文芸編集者はひとりで、十数名から三十名にも及ぶ担当作家を抱えている。その中に、デビューしたての新人から売れっ子まで含まれるのだから、よほどの熱意をその新人にもたぬ限り、つききりなどありえない。
つまり担当者はその段階では単なる発注者に過ぎないのだ。できあがってきた新人の原稿に対し何らかの可能性を感じたとき、担当者の新人へのスタンスは変化する。
スタンスの変化によってもたらされるのは、執筆の機会の増加だ。だが雑誌短篇であれ長篇出版であれ、誌面や出版計画があらかじめ決められている以上、ひとりの新人に与えられるチャンスはそう多くない。となると、新人の作品発表に対し意欲的な出版社でデビューしたかどうかが、大きな運命の分かれ目となる。
現在は多くの出版社が新人の発掘には力を入れている。長短篇さまざまな新人賞があり、ミステリ系だけで十以上は数えるだろう。
だがそれはあくまで発掘に関しての話だ。
「小説推理 2002年11月号」収録
|
| 第12回 デビュー3 |
発掘されたばかりの新人は、宝石の原石に似ている。さほど磨かなくても、すぐに商品として通用する才能もあれば、かなりの手間をかけなければ商品としての形を成さない、難しい才能もある。
小説家を目指す人間は、趣味から仕事への転換を考えて、新人賞へと応募する。それはつまり、デビューした段階では仕事になりきっていない、ということだ。ところが出版社、あるいは編集者は、当然の話だが、あくまで仕事として、小説家に接する。相手が新人であろうがベテランであろうが、作品の執筆依頼から出版が、ビジネスとして成立するかどうかを考えて、おこなう。
手間暇かけずとも商品になりやすい才能が喜ばれるのは自明の理だ。彼ら編集者が新人の作品を見るとき、即戦力たりうるものを書けるかどうかを、まず読みとろうとする。
その判断は、短篇からでは難しい。ひねりのきいたプロットを要求される短篇ミステリは、ときに交通事故的に生まれてしまい、大型新人かと思ったらあとがつづかなかったということがあるからだ。
短篇デビューをするなら、つづけて書かせてくれる出版社の新人賞を選ぶべきだ。たれ流し的に新人を生み、あとのフォローのない新人賞は避けよう。そしてなるべくなら、長篇の、それも既受賞者が活躍している新人賞でデビューする方がよい。即戦力の証明に他ならないからだ。狭き門は、くぐり抜けた者の将来を広くする。
「小説推理 2002年12月号」収録
|